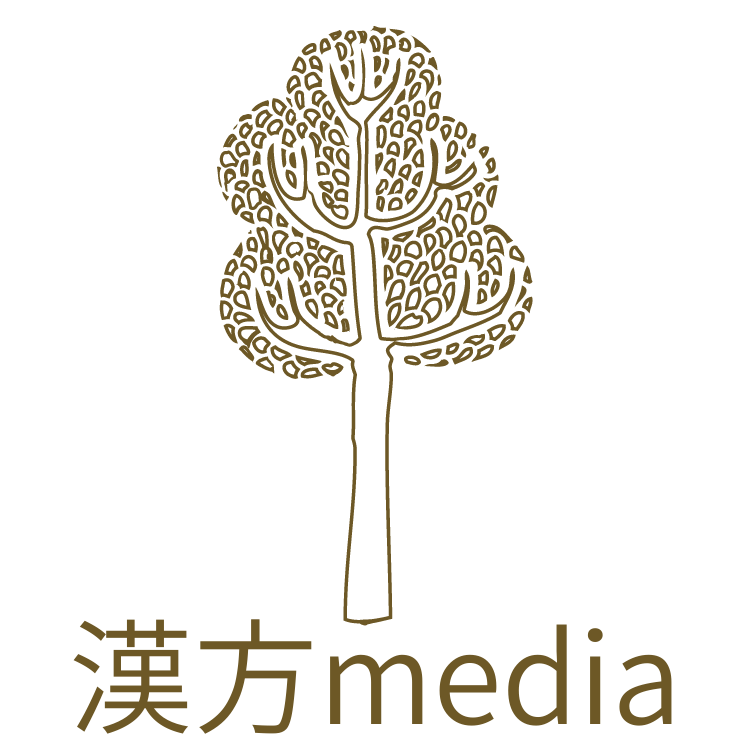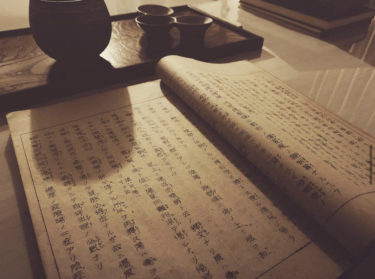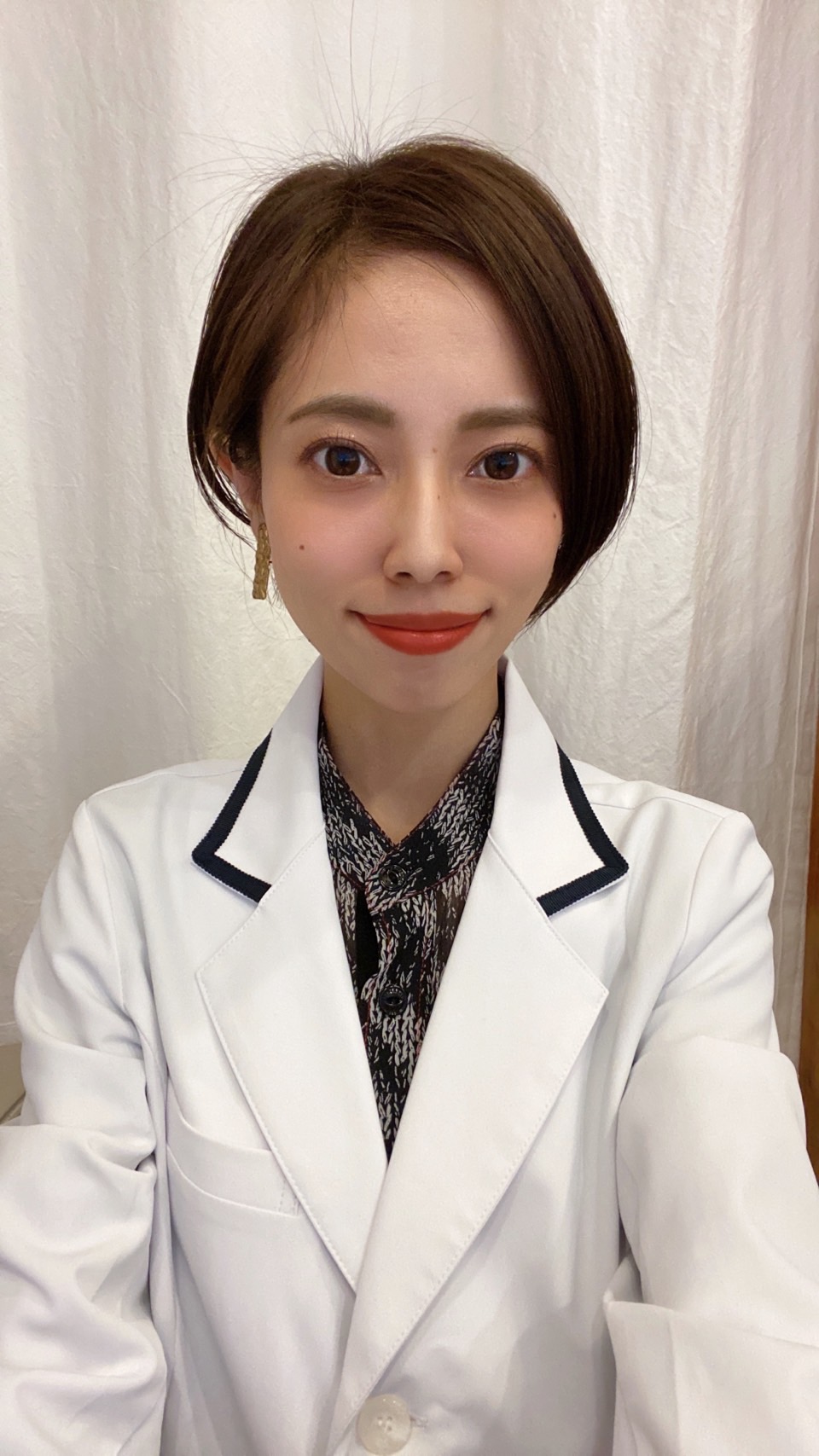鍼灸ってどんな医学?
中国3000年、日本1500年の歴史を持つ鍼とお灸を用いた医学であり、「漢方医学」の一つです。
漢方医学と言うと、漢方薬のみを示しているように思われますが、漢方医学とは、中国を起源として日本で発展した伝統医学を示し、鍼やお灸・外気治療・按摩も含まれます。
ちなみに、中国を起源として中国で発展した伝統医学を中医学と言います。起源は同じでも全く技法も理論も異なった医学体系となります。
この辺ごちゃごちゃになりやすいですよね😰
根本は同じ情報源でも、国によって表現方法も使い方も着目点も異なってくるので面白いなと思います。
日本鍼灸の流派
鍼灸にも流派が意外と多く存在しています。
この流派については、治療を受ける側からすると、治れば何だっていいよ〜的な感じなのですが😅、、、思考が技術として現れるので、そこにブレがあると技術、いわゆる治療結果にも反映される為、私的には思考の具現化の意味で大切にしています。
鍼やお灸は道具であって、その道具をどのように使いこなすのかが鍼灸師の肝です。
施術者が患者さんの身体の声や反応を読みとって経穴を選定するので、技量や感覚に拠るところが大きいのです。
極端ですが例えば、解剖生理学や神経、筋肉をベースに治療したらそれは鍼やお灸を使った西洋医学となり、経絡や気を使って外科治療したら東洋医学となります。何をベースに治療しているのか、それぞれの流派で異なってきます。
まず、漢方医学を中心とした【日本漢方派】と、中医学を中心とした【中医派】に大きく分けられます。
日本漢方派はさらに【現代派(西洋医学的)】、【古典派(経絡治療)】、【折衷派(どちらも取り入れている)】に分けられます。
中医派は【黄帝内経(こうていだいけい)】、【難経(なんぎょう)】をベースに【甲乙経(こうおつきょう)】や【脈経(みゃくきょう)】を中心に成立しています。
その中で、経絡を重視するのか、経穴を重視するのか。鍼を重視するのか、お灸を重視するのか。はたまた、全て重視するのか。と、どんどん細分化されて流派が広がっていきます。
私は御大である師匠からその辺を理解しておくといいよとご教授していただいていたので知識がごちゃ混ぜにならず勉強しやすかったです✨
黄帝内経にしても難経にしても書いてあることが違うので、情報のないままに読むと頭がこんがらがりますので。。😦

日本鍼灸の歴史
日本において中国医学伝来の端緒については、はっきりしたことは分かっていないそうですが、6世紀頃に中国から朝鮮半島を経由して伝来したと言われています。
時代とともに活躍した方も交えて見ていきましょう👀
平安時代
701年に制定された大宝律令の制度の中に『鍼生』『鍼博士』という官職が設けられ、医師などとともに当時の医学の一端を担ってきました。
『鍼生』『鍼博士』は7年間の修行期間を設けられ、「素問」「黄帝針経(霊枢)」「明堂」「脈訣」「流注図」「偃側図」「赤鳥神針経」の書の学習が要求されていました。
当時の考試に合格できる現代の鍼灸師は恐らく多くないと思います😱
…鍼はよく生人を殺すもまたよく死人を起こす…と言われるほど、専門家でない限りリスクが大きかったのです💦
平安時代820年には鍼生も薬学の知識も備えるよう課せられ、さらに927年には「太素」「新修本草」「小品方」「明堂」「難経」の5書を学ぶように定められました。
鍼博士・丹波康頼は、遣唐使によって日本に輸入された医学書をほとんど読破し、日本現存最古の医学書とされている「医心方」を984年に編纂しました。
これは遣隋使遣唐使時代の中国医学の集大成となります。
丹波康頼の鍼灸に対する思い入れもあり、千年たった現在でも中国・日本古代の医学を学ぶにはかけがえのない書の一つだと思います!
全巻は持っていませんが、婦人科疾患に関する巻数は私も持っています
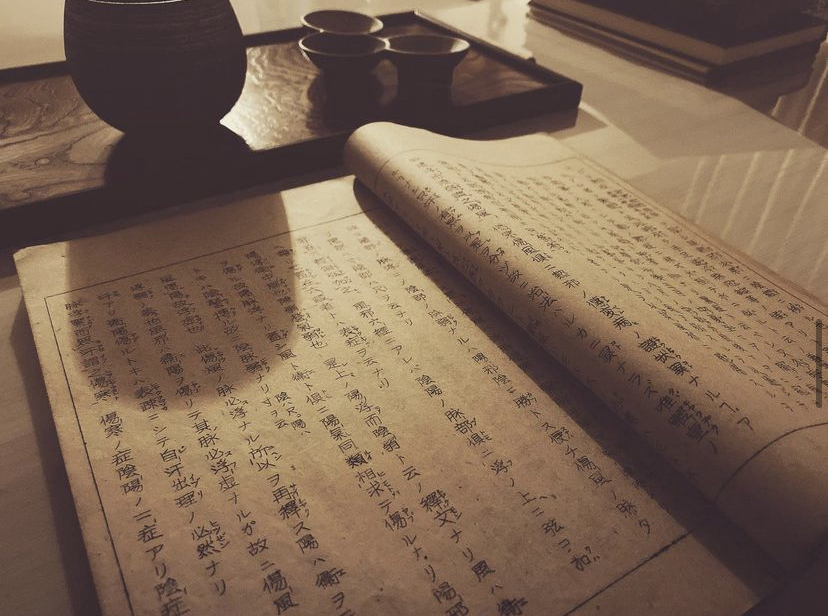
律令制が崩壊するとともに鍼医の身分制度も崩壊したので一時衰退したかのようでしたが、室町時代には独自の諸流派がどんどん生まれてきました。
この時代を想像すると立場や活躍の場を確保するのは大変だったと思います😭
安土桃山時代
安土桃山時代には、以後の漢方医学の基礎を築いた医家の曲直瀬道三が、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康らに重んじられ、日本医学中興の祖と称させるようになります。
この時代で有名なのは徳川秀忠の治病を治療し、後陽成天皇に仕えた鍼博士・御薗意斎が広めた打鍼法(鍼を小槌で叩打して刺入)です。
打鍼法の祖として夢分斎があげられることが多いですが、これはいつどのようにして始まったのか不明なことも多くまだ解明されていません。
夢分斎は多賀法印流を学んでいたのでそこからなのか。。
その為、打鍼法には「意斎流」と「夢分流」といった打鍼流派があります。
江戸時代
江戸時代になると盲人の鍼師・杉山和一の管鍼法(鍼を管に入れて突出した部分を打って刺入。現代の鍼灸で多く用いられている)が有名です。
杉山和一の生い立ちが個人的に衝撃でした。
才能を発揮できず破門になっていて、破門となるともう一度チャレンジするのってなかなか精神的に大変なのに、自分を諦めなかった杉山和一の背景に活をいれてもらった記憶があります🙏✨
鍼術の奥義を極めて開業し、さらには関東総検校(最高位の盲官)までのぼりつめ、将軍家綱・綱吉の侍医までつとめていました。
視覚障害者に対する鍼灸の指導にも力を注ぎ教育施設を開設しており、壮大な影響を及ぼしているのではないかと思います。
管鍼法は「杉山流」「入江流」「石坂流」などと受け継がれ、今でも日本の鍼術として伝え続けられていています。
現代の鍼灸と想い
知識・技術・感覚は別物です。
感覚を技術におとしこむ為に、本来は弟子入りをして師匠のもとで学ぶことが理想ですが、そのような体制はなかなか現代では取れません。
その為、古典にかかれてあるような威力を発揮できる鍼灸師は減退していると思いますが、今の時代にあった鍼灸技術が日々生まれています。美容鍼灸などはいい例ですよね。
その中でも、根強く技術を伝承しながら今に至っている流派もあります。
私は自分自身が西洋医学において病名も原因も不明の難聴を患っていることもあり、解剖生理で診るのではなく(知識としては使いますが)、自分の五感と意識を研ぎ澄ませて治療にあたりたいと思っております。
長い年月、受け継がれてきたものには、それだけの臨床と意味があります。
その意味を紐解くには相当な年月がかかるかもしれませんが、だからこそ気合いを入れて毎日毎日の鍛錬が欠かせないように感じます。
現代において鍼灸の受療率は10%もなく、痛そう、怖いといったマイナスのイメージが先行してしまっていますが、「鍼を刺す」ことが目的ではなく「気血を巡らせ経絡を通す」ことが目的です。
鍼は打てば効くのではなく、効かせることが大切です。
効かせられれば鍼を刺さなくともいいのです。
効かせる為の自分の身体作りをしなければいけないのですが、五感と意識を高める為にも気功修錬をこれからも続け深めたいと思います。