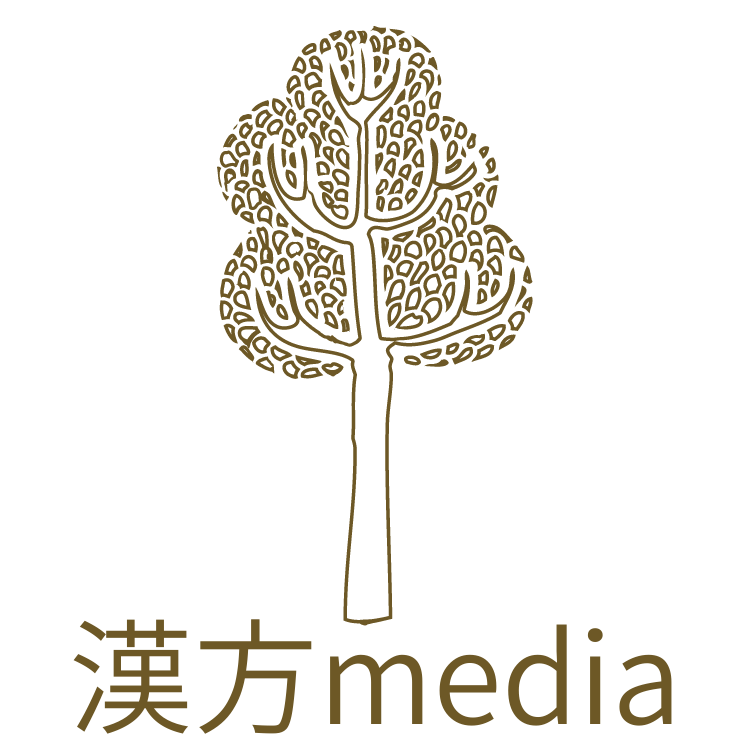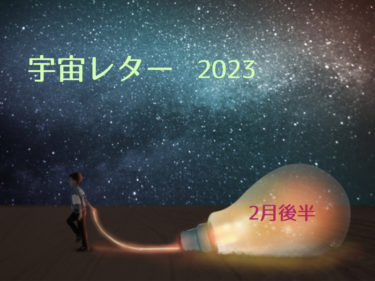今回は胃腸の大切さについてご説明したいと思います。身体に良いと言われる食べ物やサプリメントを摂っているけど、なんだか体調がスッキリしない方はいませんか?スッキリしない原因は消化力!食べ物を消化する力が低下していると、何を食べても元気になれません。自分の不調のサインに気づき、改善していきましょう。
Contents
脾胃の働きとは?
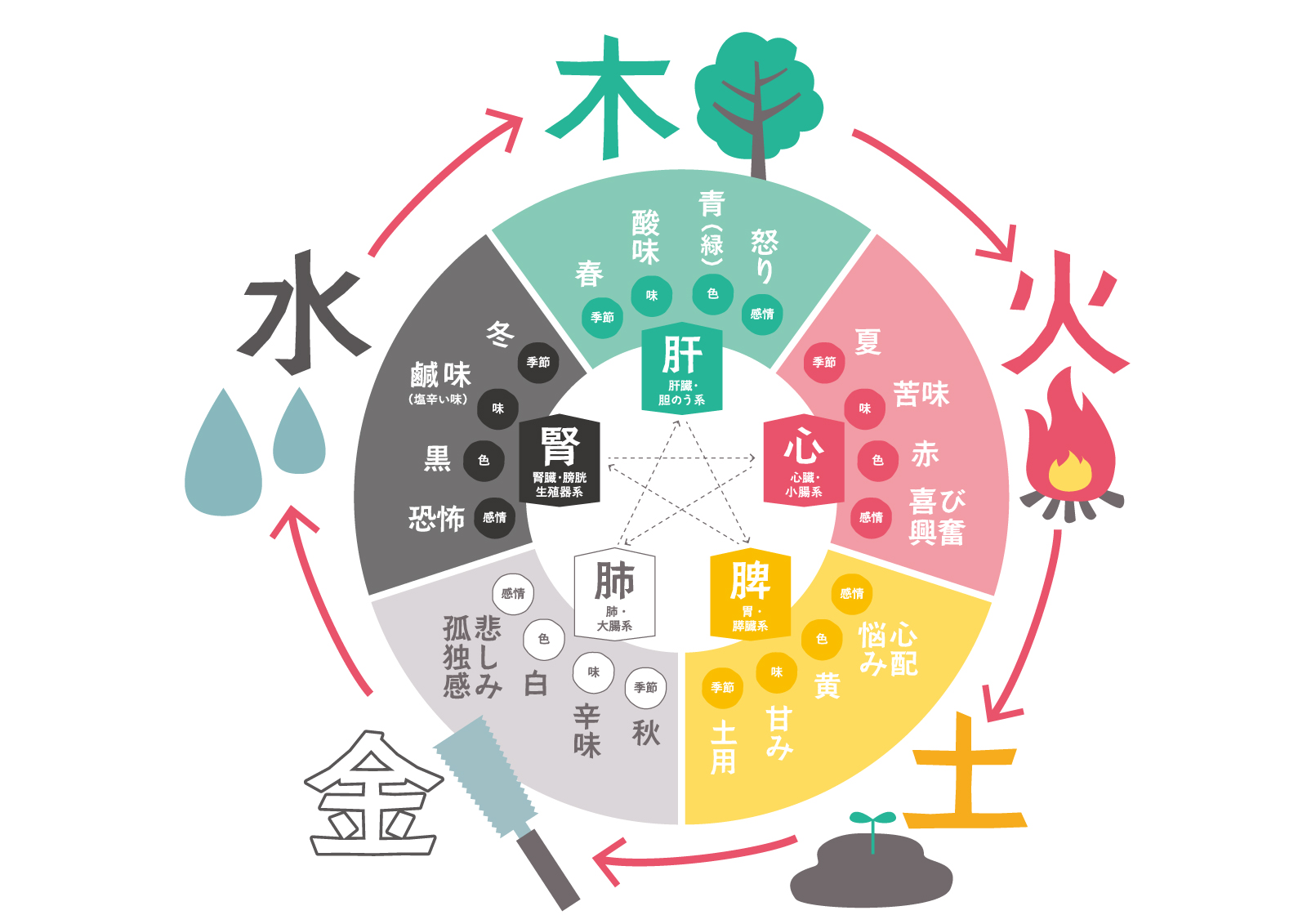
1.気血水を作り、全身に運ぶ
2.内臓の位置を正常に保つ
脾胃は身体の真ん中にあるので、小腸や大腸だけでなく、栄養素を肺などに運び上げる働きもあります。この持ち上げる働きが、内臓を持ち上げて正しい位置に保つ役割も果たしています。
3.血液が漏れないように管理する
血液が血管から漏れないようにし、正常に血液を全身に巡らせます。
脾胃のトラブルサインとは?
脾胃が弱ってくると上記の働きが低下するので、様々な不調が出てきます。
・食欲がない
・口内炎がよくできる
・風邪をよく引く
・軟便傾向
・マイナス思考
・甘い物を食べたくなる
・冷え性
など
・脱腸、脱肛になる
・目の下のたるみ
・ほうれい線がいつもより気になる
・口角が下がる
・胸が下がる
・二の腕が下がる
など
・血尿
・血便
・不正出血
・生理の出血量が多い
など
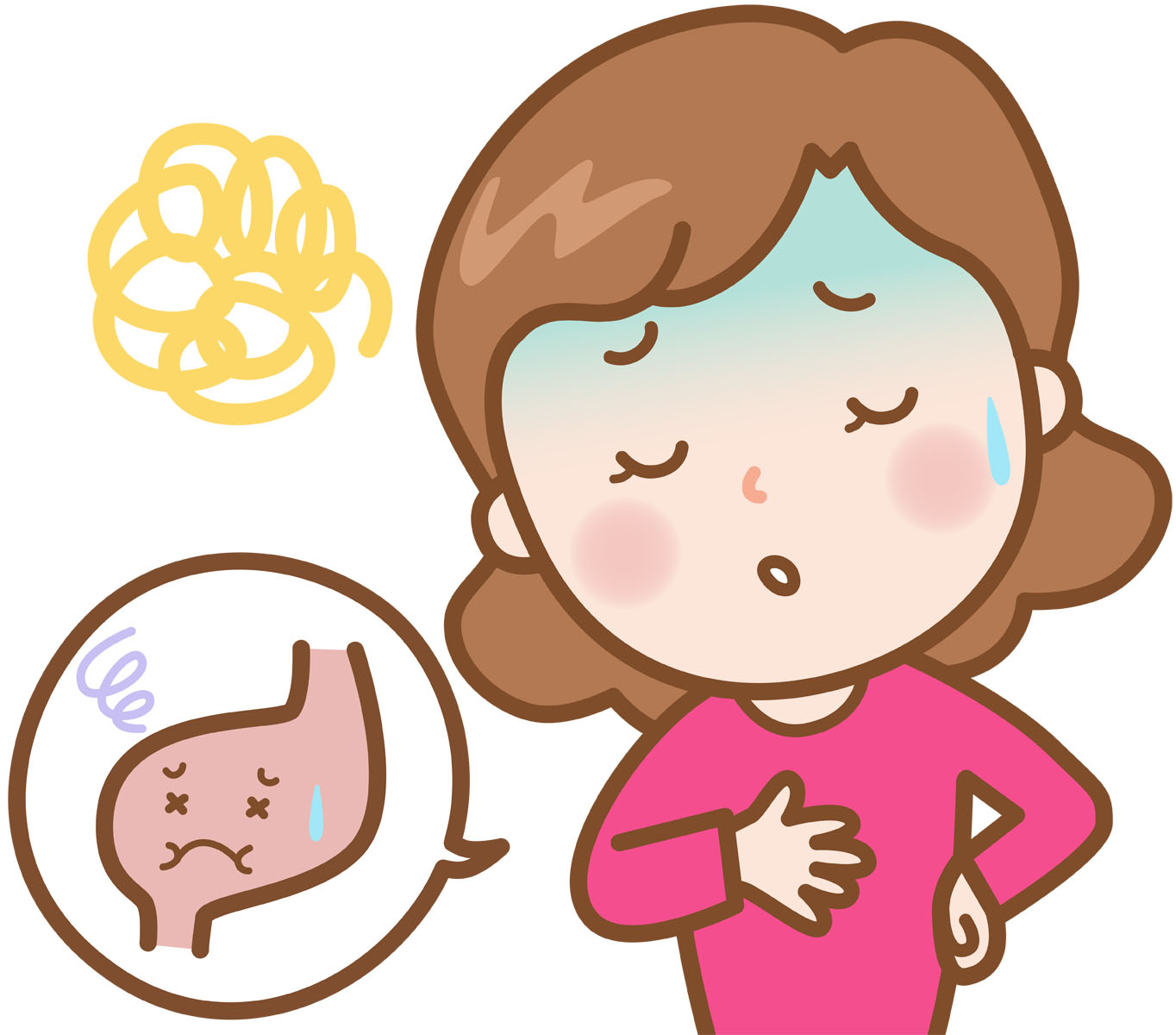
脾胃が苦手なことは避けよう!
上記のようなサインが出ている方は、脾胃が苦手なことをしていないかチェックしてみてください。
1.ストレスや緊張することが多い
2.身体が冷えている
手が冷たい方は胃腸も冷えていると言われています。胃腸が冷えていると、イメージとしては、料理をしているが、鍋に火がかからず調理ができないのと同じです。冷えていると食べた物をエネルギーに変えることができません。
3.脂ものや甘い物の食べ過ぎ

オススメ養生法
消化力を高める食べ方をする
・食前に梅干し、レモン、酢の物などの酸味のあるものを食べて、胃酸の分泌を助ける。
・一口30回以上噛んで食べて、唾液の分泌を増やす。
・食事は温かい汁物から飲んで、胃腸を温める。
・タンパク質の消化を助けるために、杜仲茶やタンポポ茶を飲む。
・早食いではなく、楽しくリラックスして食べる。
・寝る2時間以上前に食事を済ませる。(朝起きてだるい方は食べ過ぎのサインかも)
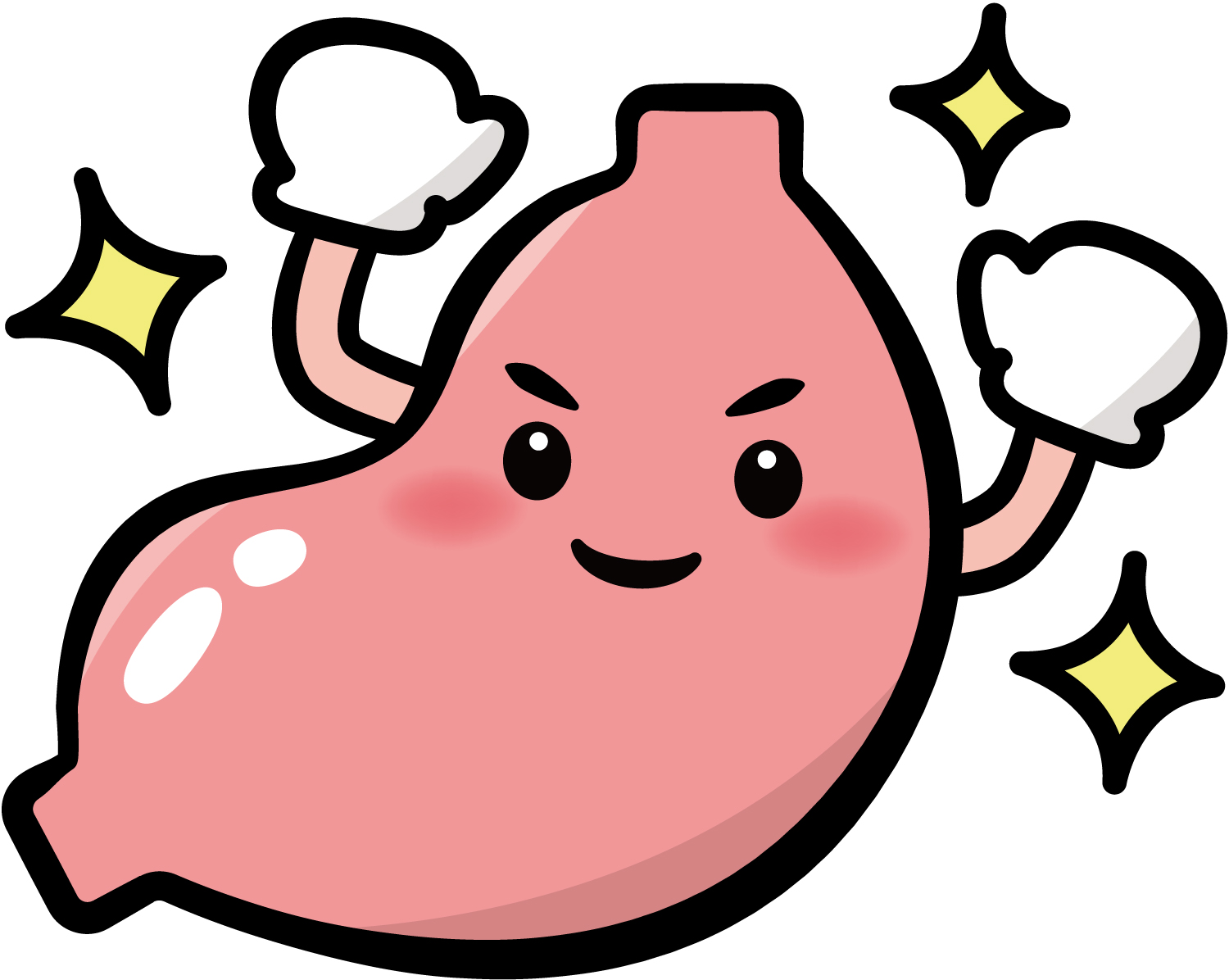
脾胃を高める食材を食べる
朝食は必ず食べる
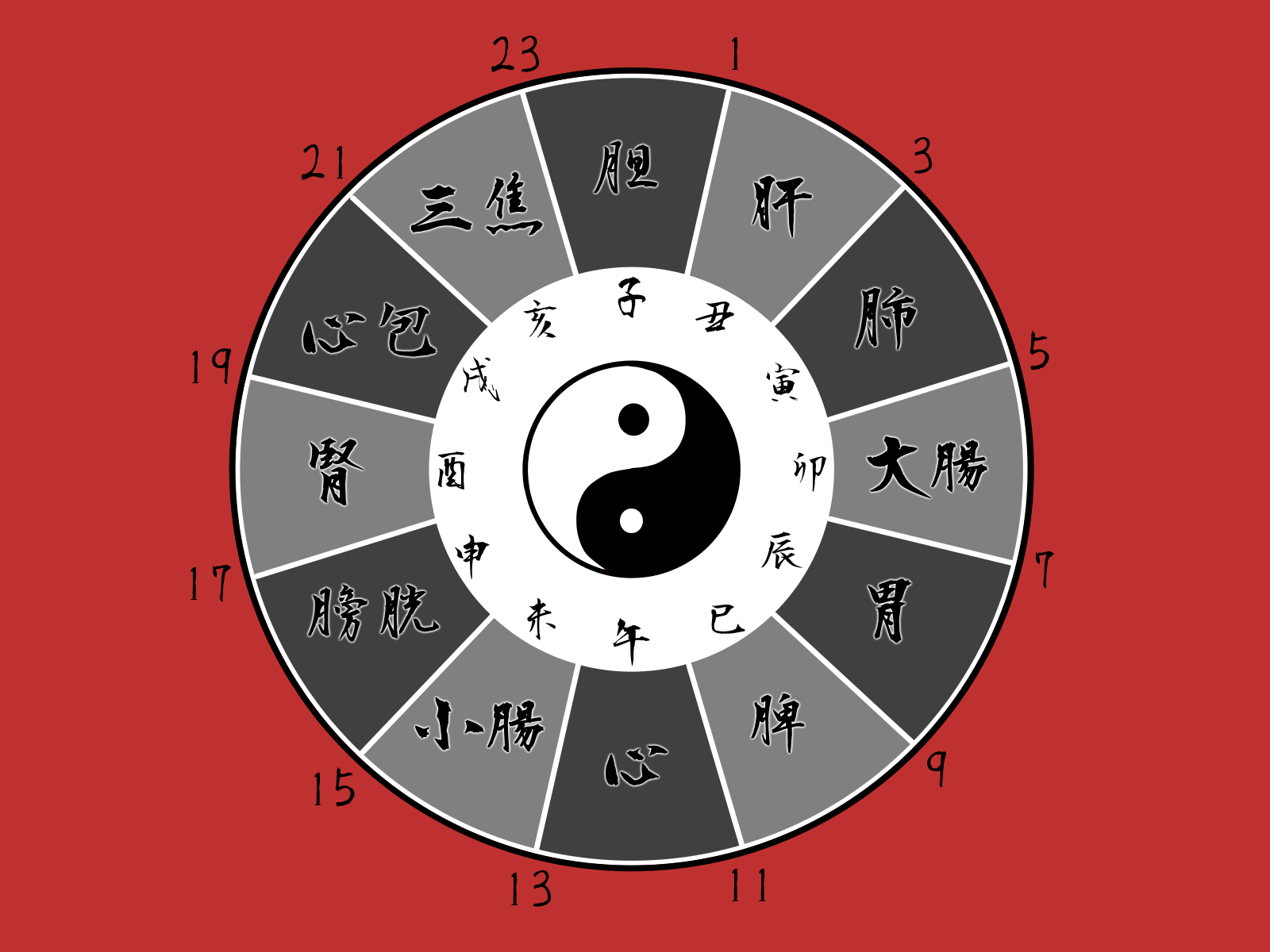
オススメ漢方薬
オススメ養生法を試しても、なかなか不調が改善されない方は、漢方薬がオススメです。
・胃腸が弱く食欲がなく、疲れやすい方にオススメ→六君子湯(りっくんしとう)
・胃腸が弱く、胃下垂や脱腸、脱肛が気になる方にオススメ→補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
【気血水】 気血水理論を学ぶ前の基礎知識 ・気血水は陰陽 陽気、陰気という言葉は 「明るい人・暗い人」を指すこともあれば 漢方の臨床では「陽の働き・陰の働き」の意味で使われもします。 もう少し具体的にいうなら[…]